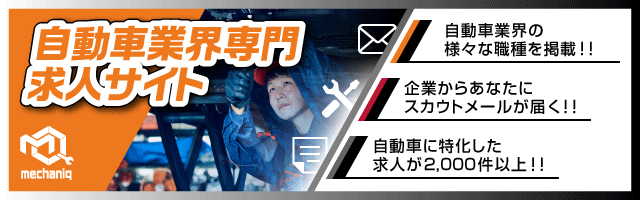自動車整備の仕事は資格がなくても可能ですが、自動車整備士の仕事は資格を取得することで業務の幅も広がります。転職の際も資格は採用を左右する重要な条件です。実務経験のある方向けの養成施設もあります。
そこで今回は、自動車整備士の仕事内容を理解し、資格の種類、取得方法、資格の難易度について解説します。自動車整備士の仕事に就きたいとお考えの方は、ぜひご一読ください。
自動車整備士とは
最初に、自動車整備士の仕事内容を具体的に説明します。
自動車整備士=メカニック
自動車整備士は「メカニック」とも呼ばれ、自動車の点検・修理、メンテナンス・調整、分解・組立などをおこなう専門的な仕事です。自動車にとって「ドクター」のような存在で、不具合があれば原因を突き止めて修理する役割を果たします。
この仕事には国家資格があり、この資格を所有して整備の仕事に携わる人を「自動車整備士」といいます。
自動車整備士の主な仕事内容
自動車整備士の仕事は「点検」「分解整備」「板金・塗装」「その他」に分かれます。
「点検」は自動車の劣化を定期的にチェックし、事故を防ぐ仕事で、法定点検(6ヵ月、12ヵ月、24ヵ月)がその代表です。
車検・修理の際にパーツを自動車から取り外し、分解して修理するのが「分解整備」。
交通事故の衝突などが原因で車両に著しい損傷が見られた場合、大がかりな分解整備が必要となります。
「板金・塗装」は、自動車のボディに関する業務で、「板金」はボディのキズ・へこみ・ゆがみなどを修復します。修復が困難な場合はパーツごと交換します。
「塗装」はボディをカラー液で塗装することで、下地処理や磨き処理も塗装の一部です。
「その他」の業務は、オプションの取り付け、タイヤ・オイルなどの交換、お客さまへの各種案内、店頭での接客、発注などの事務処理です。
自動車整備士の活躍場所
自動車整備士の職場として代表的なものは、カーディーラー(販売店)や自動車整備工場が挙げられます。
その他、中古車販売を行う中古車販売店、修理も可能なガソリンスタンドや車検工場、主に塗装修理をおこなうペイントショップなどにも活躍の場は広がっています。
また、多くはありませんが、自動車パーツなどのメーカー、損害保険会社などに就職するケースもあります。



自動車整備士資格の種類
自動車整備士の資格は、1級・2級・3級と特殊整備士とがあります。
業務の範囲は、取得している資格によって違ってくるので、どのような仕事をしたいのかで必要な資格も変わってきます。資格の取得を考える際は、慎重に判断しましょう。
以下では、それぞれの資格の特徴を解説します。自分の目指すキャリアプランに合った整備士資格を見極めてください。
3級自動車整備士
3級自動車整備士には、「3級自動車ガソリン・エンジン整備士」「3級自動車ジーゼル・エンジン整備士」「3級自動車シャシ整備士」「3級二輪自動車整備士」の4種類があります。資格名に表記されているように、それぞれガソリン車・ディーゼル自動車・シャシ(自動車のエンジン・ボディを除いた箇所)・二輪自動車の整備に特化しています。主に点検業務やカー用品の取り付け、エンジンオイルやギアオイル交換、タイヤ交換など、基本的な整備をおこないます。
エンジン、ブレーキ、サスペンションなどの分解整備は、3級自動車整備士は単独でおこなうことはできません。

2級自動車整備士
2級自動車整備士は、自動車の定期的なメンテナンスや点検、分解整備なども可能な資格です。2002年に1級自動車整備士試験が新設されるまでは、最上位の資格でした。整備工場で働く整備士の多くが所有しており、ほぼすべての整備業務が可能な資格です。「2級ガソリン自動車整備士」「2級ジーゼル自動車整備士」「2級自動車シャシ整備士」「2級二輪自動車整備士」に分かれています。

1級自動車整備士
1級自動車整備士は一般的に「1級小型自動車整備士」を指します。2002年に新設された資格試験で、このほかに「1級大型自動車整備士」「1級二輪自動車整備士」もありますが、試験が実施されたことはまだありません。
従来の2級資格で整備に関する業務はほとんどおこなうことができるので、1級を取得しても、現場の業務内容に大きな変化はありません。1級自動車整備士には、ハイブリッド車や電気自動車などに関する専門知識や予防安全技術にも対応が求められ、環境問題・安全管理面でも2級以上に踏み込んだ法令知識などが必要になってきます。
また、1級自動車整備士には、整備士のリーダーとして、多くの職場で整備士の指導・育成も期待されます。

特殊整備士
特定のパーツを専門とする資格取得者を、特殊整備士といいます。
特殊整備士には、「自動車タイヤ整備士」「自動車電気装置整備士」「自動車車体整備士」の3種類があり、資格によって整備をおこなう箇所が違ってきます。1・2級資格を取得すればほとんどの整備ができますが、特殊自動車整備士資格があると、特定のパーツを専門的に整備することができるようになります。

自動車整備士の資格を受験するための条件
自動車系ではない通常の学校を卒業した場合
工業高校や大学の機械科を卒業した場合は、6ヵ月以上の実務経験で3級自動車整備士の受験が可能になります。また、高校の普通科や大学で機械科などを専攻していない場合は、卒業後に整備工場などで1年以上の実務経験を積めば、3級自動車整備士の受験資格が得られます。
自動車系の学校を卒業した場合
工業高校の自動車科(3級整備士養成課程)に進んだ場合、卒業と同時に3級自動車整備士の受験資格を得られます。終了後2年間は実技試験が免除されるので、その間の受験科目は学科試験(筆記)だけになります。
養成施設に通うと、終了時に1・2級の受験資格も得られますが、詳しくは「自動車整備士の資格を取るためには」の項で解説します。
必要な実務経験
受験資格を得るために必要な実務経験は、以下の通りです。実務経験を積んで受験する場合は、実技試験の免除がないので注意してください。
| 資格の種類 | 必要な実務経験 |
| 3級自動車整備士の受験資格 | 中学・高校・大学卒業後に実務経験1年以上 機械関係卒の場合は実務経験6ヵ月以上 |
| 2級自動車整備士の受験資格 | 3級資格取得後に実務経験3年以上 |
| 1級自動車整備士の受験資格 | 2級資格取得後に実務経験3年以上 |
| 特殊整備士の受験資格 | 普通科の中学・高校・大学を卒業した場合→実務経験2年以上 自動車整備系の専門学校・認定大学を卒業(2級整備士課程)の場合→実務経験1年以上 自動車整備系の専門学校・認定大学を卒業(特殊整備士課程)の場合→実務経験不要 |
自動車整備士資格の難易度と合格率

この章では、それぞれの資格の試験内容と難易度について解説します。
3級自動車整備士の難易度
試験科目は学科と実技です。
学科試験は30問(60分)で、4択のマークシート方式です。合格率は60%~70%台で推移しています。自動車整備の専門学校を卒業した受験者が多い2級の学科試験の合格率(おおむね90%台)と比べると、独学で受験する一般受験者が多いせいか、合格率はやや低くなっています。
2級自動車整備士の難易度
学科試験と実技試験があります。
学科はすべて4択マークシート方式で、40問(80分)になります(自動車シャシ整備士のみ30問(60分)になります。
前述したように、合格率はおおむね90%台で推移しており、3級よりやや高めです。
1級自動車整備士の難易度
学科試験は筆記試験と口述試験に分けられます。
筆記試験は50問(100分)で、実技試験もおこなわれます。難易度が高く、令和3年(2021)の合格率こそ50%台に跳ねあがりましたが、前年度の合格率は30%台です。出題範囲が広いので、整備士養成課程のある大学・専門学校の合格率はかなり高くなっているようです。
特殊自動車整備士の難易度
特殊自動車整備士の合格率はほとんどの場合において50%以上で推移していますが、年度によっては50%台を切る年もあります。
出典:令和3年度第2回(第104回)自動車整備技能登録試験「学科試験」の試験結果について
自動車整備士の資格を取るためには

ここでは、自動車整備士の資格を取得する方法を解説します。
専門学校(養成施設)に通う
大学、短大、専門学校などで「自動車整備学校」と認定されている施設(学校)を「1種養成施設」といいます。主に2級もしくは3級の受験資格を得るための養成施設ですが、1級のための養成コース(4年制)を備えた施設もあります。
2級整備士養成課程(2年制)に進むと、卒業と同時に2級整備士の受験資格を得られ、受験時の実技試験は免除されます。 1種養成施設の入学資格は表のようになります。
| 課程 | 入学資格 | 修業年限 |
| 3級自動車整備士養成課程 | 入学資格は中学卒業以上 | 1年以上 |
| 2級自動車整備士養成課程 | 入学資格は高校卒業以上 | 2年以上 |
| 1級自動車整備士養成課程 | 2級ガソリン自動車整備士または2級ジーゼル自動車整備士取得者 | 3年以上 |
| 1級自動車整備士養成課程 | 2級ガソリン自動車整備士と2級ジーゼル自動車整備士の両方取得者 | 2年以上にすることが可能 |
自動車整備技術講習「二種養成施設」を受講する
全国に53施設あり、各都道府県自動整備振興会の自動車整備振興会技術講習所が二種養成施設にあたります。自動車の整備作業に関しての実務経験がある人が対象となる施設で、自動車整備工場などで働きながら受講する方が多く、夜間や休日などに講習を行っている施設もあります。
期間は前期が4月から、後期が9月からとなっており、養成課程は登録試験の種類や実施時期に合わせての対応です。
2級及び3級自動車整備士養成課程の修業年限は6か月です。
1級大型及び1級小型自動車整備士の養成課程の入校資格は、2級ガソリン自動車整備士又は2級ジーゼル自動車整備士を取得しているもので、修業年限は1年6か月以内とされています。なお、2級ガソリン自動車整備士及び2級ジーゼル自動車整備士の両方を取得している方は修業年限を1年以内にすることが可能です。
この養成施設の所定の課程を修了すると、実技試験の免除(修了後2年間)となります。
出典:国土交通省 自動車整備士養成施設について
専門学校に通わず未経験でも整備士になれるのか?
専門学校の整備士養成課程に進まなくても、実務経験が1年以上あれば、3級自動車整備士の受験資格を得られます。
高校の普通科を卒業して、整備工場などに就職した場合はこのルートになります。実技経験の免除はなく、学科試験と実技試験の両方に合格する必要があるので注意してください。
自動車整備士の資格取得の流れ
自動車整備士になるためには一定の受験を満たしたうえで国土交通大臣の行う自動車整備士技能検定を受け、合格しなければなりません。ただし、国土交通大臣の登録を受けた期間が行う登録試験を受験し、合格後に免除申請を国土交通省(実際には各都道府県の自動車整備振興会)に提出することで検定試験に合格したとみなされ、自動車整備士の資格を取得することができます。
検定試験(国土交通省)もしくは各都道府県の自動車整備振興会に申し込む
受験資格を満たした上で検定試験の申込を行います。もしくは自動車整備振興会の登録試験の申込を行います。
自動車整備士技能検定を受ける
検定試験・登録試験を受けます。自動車整備振興会の登録試験の学科試験合格者は検定試験の学科試験免除、実技試験の合格者もしくは養成施設等の修了者(一種二種養成施設)は実技試験免許を免除申請することが可能です。
合格後、各都道府県の自動車整備振興会で申請手続き
必要書類は以下になります。
申請用紙
実務経験証明書(整備の実務経験年数を証明するもの※事業者の押印、整備士手帳等)
登録試験の合格証書、または合格通知のはがき
技術教習所の修了証書または整備学校の卒業証書、整備士手帳など
2級整備士合格証書(1級受験の方)
3級整備士合格証書(2級受験の方)
申請者の宛先を記入したはがき
申請料
印鑑(認印)
免除申請の有効期限は合格後2年間となります。有効期限がすぎると免除はされなくなるため、すぐに届出に行くようにしましょう。
取得する資格(1~3級等)や卒業した学校(自動関連の学校かそれ以外か)にもよって必要な書類等は変わります。詳しくは各都道府県の自動車整備振興会にお問い合わせください。
国土交通省から合格証明書を交付される
国土交通省から合格証明書が交付され、資格が取得できます。
自動車整備士の魅力や向いている人は?
自動車整備士の仕事の魅力や適性を理解しておきましょう。
専門知識・技術が身につく
整備のプロとして専門知識・技術が身につきます。現場での経験やセンスが問われるような場面も多く、奥が深い仕事です。
事故を防ぐという責任感が持て、やりがいがある
自動車は、もはや生活に欠かせない存在になっています。とりわけ、地方などでは、車がないと不便で、買い物をするにも苦労するというような声を耳にしたことのある人も多いでしょう。
生活には欠かせない自動車ですが、他方では、運転を誤って接触事故や衝突事故を起こしてしまえば、自分だけでなく、誰かの人生をも左右してしまうことになりかねません。
自動車整備士は、生活基盤を支え、事故を未然に防ぐためにも、なくてはならない責任のある仕事です。誰かの生活の役に立ち、安全に貢献する仕事には、自動車整備士の誰もがやりがいを感じているでしょう。
おわりに
自動車整備士の仕事や資格の種類、取得の仕方、受験の難易度などについて説明しました。
自動車整備士は、専門知識が必要なだけでなく、ユーザーの安全に直接つながる社会的意義のある仕事です。自動車が好きで、集中力と発想力があり、コミュニケーション能力のある人にはぴったりといえるでしょう。ハイブリッドや電気自動車などの普及に合わせ、自動車整備士の需要は今後ますます高まっていくと思われます。