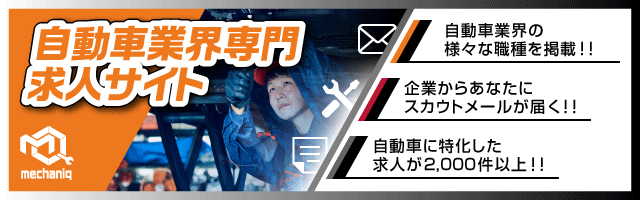自動車整備士の主な仕事の1つである分解整備ですが、この分解整備という名称が「特定整備」に変更となりました。名称の変更に伴い、認証工場にはいくつかの対応が必要になりましたので、本記事では従来の分解整備と特定整備の違いや、新たに認証が必要となった作業、認証工場になるためにとるべき対応について解説します。
すでに「特定整備制度」を盛り込んだ道路運送車両法は2020年4月から施行されているので、早めにチェックしておきましょう。
従来の分解整備とは
新しい内容の前に、まずは従来の分解整備の内容を整理しておきましょう。分解整備とは何なのか、分解整備の作業範囲についてご説明します。
分解整備とは
分解整備とは、自動車整備士がおこなう「点検整備」「緊急整備」「分解整備」の3つの整備のなかでも高度な技術を要する整備で、2級自動車整備以上が担当できる整備です。自動車の安全な走行に直結する部分の整備ということで、道路運送車両法による認証制度があるほど重要視されているのが特徴です。
整備工場によっては分解整備を請け負っていないところもあるなど、整備工場や整備士のレベルを測る1つの基準となるといってもいいでしょう。
分解整備の範囲
分解整備の作業範囲は、以下の7つの種類が挙げられます。エンジンや足回りなど、自動車の安全性や環境保全に繋がる部分であることが分かるでしょう。
- 原動機:エンジン交換など
- 動力伝達機:クラッチ、ミッション、プロペラシャフト、デフの取り外し、交換など
- 走行装置:ドライブシャフトやアクスルシャフト、ロアアームの取り外しなど
- 操縦装置:ステアリングのギヤボックスや、タイロッドの取り外しなど
- 制動装置:ブレーキパイプやブレーキホースの取り外しなど
- 緩衝装置:リーフスプリングの取り外しなど
- 連結装置:牽引自動車の連結部分の取り外しなど
今回の制度変更の概

「分解整備」から「特定整備」に名称が変わったと述べましたが、なぜ名称が変わったのか、名称以外にどこが変わったのでしょう。制度変更の背景やタイミング、変更された内容についてご紹介します。 すでに制度自体は施行されていますが、以下で特定整備制度についての理解を深めましょう。
制度変更の背景
特定整備制度施行の背景として、自動車技術の発展が挙げられます。これまで時代やニーズに合わせて日々進化していた自動車ですが、特に近年の発展は著しく「100年に1度の大変革期」と呼ばれているほどめざましい発展を遂げています。
その変革の大きな要となったのが、自動運転や衝突被害軽減ブレーキなどを実現した電子制御装置の拡大・発展です。安全走行に大きな影響を与える電子制御装置ですが、従来は自動車の走行の安全性を左右する装置の整備を指す「分解整備」に含まれていませんでした。認証を受けてなくても電子制御装置の整備が可能だった分解整備制度では、現代の車の安全性を確保するのは難しいため、法改正に踏み切られたという背景があります。
制度変更のタイミング
2019年(平成31年・令和元年)5月に交付された特定整備制度は、2020年(令和2年)4月1日から施行されています。すぐに対応をとらないと法律違反になるわけではなく、4年間の経過措置期間が設けられています。
詳しくは後述する「認証工場に必要な対応」の項で解説しますので、そちらをご覧ください。
変更された内容
特定整備制度では、以前までの分解整備の範囲が拡大し、電子制御装置整備が追加されたことが変更点となります。なお、特定整備制度であっても、従来の分解整備の内容が含まれることには変わりありません。
新たに認証の必要となった作業
自動車の安全な走行を守るために、新たに認証が必要になった電子制御装置整備ですが、対象となる作業範囲を以下で確認しておきましょう。
電子制御装置整備とは
電子制御装置整備とは、分解整備の基準と同じく、自動車の安全な走行に直結する、高度な技術を要する整備のことを指します。主に以下の3つの作業が挙げられます。
- 自動運行装置の取り外しや、作動に影響を及ぼすおそれがある整備・改造
- 自動ブレーキやレーンキープ機能に用いられる、前方をセンシングするためのカメラ等の取り外しや機能調整(コーディング作業や光軸調整など)
- 1、2に関するカメラやレーダー等が取り付けられているバンパ、グリル、窓ガラスの脱着
特定整備に関わる変更点・サポート
特定整備制度により、作業場の改築や整備士の増員が必要であるか否かが気になる事業所も少なくないと思われます。ここでは、特定整備に関する変更点や受けられるサポートについてご紹介します。
電子制御装置整備をおこなう予定のある事業所においては、以下をチェックしておきましょう。
必要な作業場面積
特定整備に必要な作業場面積は、以下のとおりです。なお、ここでご紹介する作業場面積は、普通自動車の場合の認証基準となります。
| 電子制御装置点検整備作業場 | 間口 | 2.5m |
| 奥行き | 6m(屋内3m) | |
| 天井高さ | 対象とする自動車についてエーミング作業を実施するのに十分であること | |
| 床面は平滑であること | ||
| 車両置場 | 間口 | 3m以上 |
| 奥行き | 5.5m以上 | |
必要な設備・道具
特定整備で新たに必要になる主な設備や道具は、以下になります。
- 水準器
- 整備用スキャンツール(性能および機能要件を規定)
ほかにも、点検・整備に係る機器や法令の情報や自動運転装置の技術情報を入手できる体制をとることが義務づけられています。
従業員に関する基準
基本的に、従業員に関しても分解整備で定められていた工員数や自動車整備士の最低条件と同じです。変更点としては整備主任者の資格要件が挙げられます。従来の整備主任者の要件に加え、講習の受講が必須になります。
また、分解整備と特定整備の両方をおこなう場合、「1級自動車整備士(1級二輪は除く)」 または 「1級二輪自動車整備士、もしくは、2級自動車整備士」であって、講習を受けた者のみが整備主任者として選任が可能になります。ただし、こちらも経過措置があります。詳しくは後述する「認証工場に必要な対応」の項をご覧ください。
運輸支局長等による講習
特定整備制度にいち早く対応するため、すぐにでも認証が欲しいと考えている事業所もあるでしょう。そこで、当面の間、運輸支局長等による講習を受講することで、整備主任者の要件を満たすことのできる対策が講じられています。
法令などを学ぶ「学科」とエーミング作業などを学ぶ「実習」の2項目の講習を受けたあと、筆記試験による試問を受けて合格することで、整備主任者として選任が可能になります。
なお、自動車検査員研修や整備主任者研修において、2020年(令和2年)度以降におこなわれるもので、かつ、学科講習の内容が含まれているものを受講すれば、学科講習を受講したものとして見なされます。また、実習講習においても、各自動車整備振興会やディーラーなどでおこなわれるエーミング講習の受講をはじめ、過去に受講したエーミング講習であっても、実習講習を受講したものとして見なされます。
認証工場に必要な対応

それでは、認証工場になるにはどのような対応をとれば良いのでしょうか。ここでは特定整備制度の経過措置や認証工場となるための認証パターンについて解説します。
経過措置について
前述したとおり、特定整備制度には4年間の経過措置期間が設けられています。ただし経過措置として認められるのには条件があるので、以下を確認しましょう。
2020年(令和2年)3月31日までに、今回新しく認証が必要となった電子制御装置の整備をおこなったことがある事業所については、2024年(令和6年)3月31日まで、引き続き電子制御装置の整備をおこなうことができます。
2020年(令和2年)3月31日までに電子制御装置の整備をおこなったことのない事業所については、新たに電子制御装置整備の認証を受ける必要があります。
また、整備主任者の資格要件に関しても1年間の経過措置が設けられています。こちらも条件があるので、以下を確認しておきましょう。
- 資格要件を満たしている整備主任者が、事業所内に1人以上いること
- 2021年(令和3年)までに講習を修了する内容を記した計画書を提出すること
なお、2021年(令和3年)3月31日までに講習を修了しなかった場合、整備主任者の選任は解除されてしまいます。期日までに講習を修了するようにしましょう。
特定整備の認証パターン
特定整備制度の認証パターンとして、以下の3つが挙げられます。顧客のニーズや事業所の設備、技術などを鑑みて、どの認証パターンにするかを決めましょう。
- 従来の分解整備のみ
特に必要な手続きはありません。 - 電子制御装置整備のみ
新たな認証が必要です。 - 分解整備および電子制御装置整備の両方
新たな認証が必要です。
おわりに
自動運転や衝突被害軽減ブレーキなど、自動車の安全走行に重要となる電子制御装置整備の安全性を確保するため、法改正がおこなわれて導入されたのが特定整備制度です。特定整備制度への移行については経過措置がとられているとはいえ、今後特定整備をおこなうためには新たな要件や認証を満たす必要があります。今回ご紹介した内容を参考に、できるだけ早く認証を得るよう対応を進めましょう。