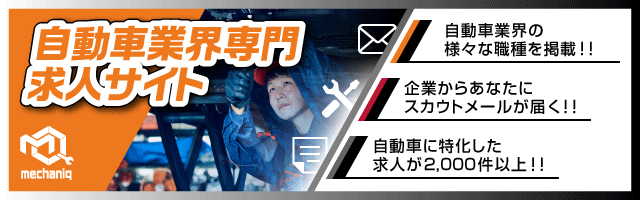整備士の就職先として最も多い自動車整備工場には、「認証工場」と「指定工場」の2種類があります。それぞれ仕事内容が異なるため、どちらを選ぶかは好みや能力などによって適性が異なります。
そこで本記事では、認証工場と指定工場の違いや仕事内容をご紹介します。これから整備工場に就職しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
認証工場と指定工場の違い
まずは、認証工場と指定工場について見ていきましょう。
認証工場とは
自動車の分解整備を行うためには、地方運輸局長の「認証」を受けなければなりません(道路運送車両法第78条)。この認証を受けて点検整備・修理が行えるのが認証工場です。
認証工場では、「点検整備」「緊急整備」「特定整備」の主に3つの役割があります。点検整備には、自動車に劣化や不具合などがないかを点検・整備するほか、オイル交換やタイヤ交換なども含まれます。緊急整備では、事故による故障やアクシデントが起こった際に部品の交換・修理が行われます。特定整備は、自動車の安全走行に大きく影響を与えるエンジンやミッション関係の装置を分解して整備する作業です。
指定工場とは
認証工場のなかでも、自動車の整備において一定の基準を満たす設備、技術、管理組織のほか、自動車の検査の設備と検査員を選任している工場に対し、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。指定工場になるには、充実した設備や高度な技術など厳しい認定基準を満たす必要があります。
指定工場では、点検・整備に加えて車検まで一貫して行うことが可能です。そのため、認証工場よりも短時間で車検を終わらせられるという特徴があります。
認証工場と指定工場の違い
認定工場と指定工場はどちらも整備工場ですが、5つの異なるポイントがあります。それぞれの違いは、以下の通りです。
地方運輸局長からの承認の有無
認証工場とは地方運輸局長からの承認を得て、車を分解して整備・点検が可能な「特定整備」(※)を行うことができる工場です。認証工場の承認を得た上で、さらに申請を行って地方運輸局長に「指定自動車整備事業」の指定を受けると、指定工場となります。
※「特定整備」:2020年4月より「分解整備」から名称変更
従来の分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造:道路運送車両法第49条第2項、同施行規則第3条)に、電子制御装置整備が加わり、名称も「特定整備」に変更されました。施行から4年間の経過措置期間があり、従来通りの分解整備のみを行うパターンの認証も可能です。
指定工場に指定されるには設備、技術、管理組織等で一定の基準を満たす必要があるため、認証工場の承認を受けるよりも狭き門だと言えるでしょう。
業務範囲
認証工場では車検のための点検・整備や、特定整備を行うことができますが、工場内で車検のための検査をすることはできません。対して指定工場では、特定整備から車検の検査まで行うことが可能です。検査が終了すれば書類を陸運局に提出し車検証が発行されるため、認証工場で必要な整備後に車検場に持ち込む必要がありません。
必要な作業場
認証工場と指定工場で必要な作業場は、以下の通りです。
| 認証工場 | 指定工場 |
| l 車両整備作業場
l 部品整備作業場 l 点検作業場 l 車両置場 |
l 現車作業場
l 部品整備作業場 l 完成検査場 |
出典:関東運輸局ホームページ
必要な設備
認証工場と指定工場で必要な設備は、次の表の通りです。
| 機械設備名 | 原動機 | 動力伝達装置 | 走行装置 | 操縦装置 | 制動装置 | 緩衝装置 | 連結装置 | |
| 作業機械 | プレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エア・コンプレッサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| チェーン・ブロック | ○ | ○ | ||||||
| ジャッキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 充電器 | ○ | ○ | ||||||
| 作業機械 | ノギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トルク・レンチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 点検計
器およ び点検装置 |
サーキット・テスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重計 | ○ | |||||||
| コンプレッション・ゲージ | ○ | |||||||
| ハンディ・バキューム・ポンプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| エンジン・タコ・テスタ | ○ | ○ | ○ | |||||
| タイミング・ライト | ○ | |||||||
| シックネス・ゲージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイヤル・ゲージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トーイン・ゲージ | ○ | ○ | ○ | |||||
| キャンバ・キャスタ・ゲージ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ターニング・ラジアス・ゲージタイヤ・ゲージ | ○ | ○ | ○ | |||||
| タイヤ・ゲージ | ○ | |||||||
| 検車装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 一酸化炭素測定器 | ○ | |||||||
| 炭化水素測定器 | ○ | |||||||
| 工具 | ホイール・プーラ | ○ | ○ | |||||
| ベアリング・レース・プーラ | ○ | ○ | ○ | |||||
| グリース・ガンまたはシャシ・ルブリケータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 部品洗浄槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
出典:国土交通省ホームページ
分解整備と電子制御装置整備の両方を行う場合には下記が必要
- 電子制御装置点検整備作業場
- 整備用スキャンツール
- (水平面を確認するための)水準器
- 整備要領書等の点検整備に必要な情報の入手体制
出典:国土交通省ホームページ
指定工場では上記に加え、以下の設備が必要となります。
- ホイール・アライメント・テスタまたはサイドスリップ・テスタ
- ブレーキ・テスタ
- 前照灯試験機
- 音量計
- 速度計試験機
- 一酸化炭素測定器
- 炭化水素測定器
- 黒煙測定器またはオパシメータ
必要な人材

認証工場と指定工場では、必要とされている人員も異なります。必要な有資格者や人員数は、以下の通りです。
| 認証工場 | 指定工場 | ||
| 2人以上 |
|
4人以上 |
|
※分解整備と電子制御装置整備の両方を行う場合
- 2名以上、うち1名は『一級自動車整備士(二輪除く)』又は『一級二輪自動車整備士若しくは二級自動車整備士であって、国が定める講習を受講した者』
- 従業員に対する、自動車整備士数の割合が1/4以上であること
出典:国土交通省ホームページ
結局どちらの工場が良い?
整備士を志望している方のなかには、認証工場と指定工場のどちらで働くべきか悩んでいる方も多いでしょう。ここでは、それぞれの工場での業務に向いている人の特徴をご紹介しますので、工場を選ぶ際の参考にしてみてください。
認証工場での業務に向いている人
認証工場で働く上で重要なのは、観察眼のするどさだと言えるでしょう。認証工場での仕事内容は、点検整備・緊急整備・特定整備といった整備業務がメインです。1つのミスが自動車事故や故障などの危険を招いてしまうので、細かい部分に気付く注意力や仕事に対する丁寧さが必要になります。
また、自動車の整備では大きな部品の交換などの力仕事も多いため、体力があることも重要です。さらに、お客さんに車の整備・修理内容を説明する機会もあるため、ある程度コミュニケーション能力もあった方が良いでしょう。
指定工場での業務に向いている人
指定工場では、基本的に認証工場と仕事内容の共通する部分も多く、観察眼や体力、コミュニケーション能力は指定工場で働く上でも重要視されます。
指定工場では、点検整備・緊急整備・特定整備に加えて車検検査まで、自動車の整備全般を扱っています。そのため、業務を一から学びたい方や初めて整備工場で働く方に向いています。また、車検検査の最終段階である「完成検査」ができる自動車検査員を目指す方も、指定工場が向いていると言えるでしょう。
ただし、指定工場のなかには車検取得やそのための整備を中心に行っていて、修理を行っていない工場もあります。工場によって仕事内容が大きく異なる可能性があるので、車検検査の他に故障修理やオイル交換などの簡単な作業も請け負っているか事前に確認しておく良いでしょう。
おわりに
自動車の点検・整備を行うことのできる認証工場と指定工場は、どちらも地方運輸局長の承認を得ている点では同じですが、車検検査が可能か否かという点で大きく異なります。修理や整備などを中心に行いたい場合は認証工場を、自動車の修理から車検検査まで整備全般を行いたい場合には指定工場を選ぶと良いでしょう。
しかしながら、認証工場と指定工場のどちらが自分に向いているのか、どの工場が良いのか悩んでしまう方も多いでしょう。その場合は株式会社レソリューションが提供している求人サイトがおすすめです。メカニックの求人情報に特化しているので、自分に合った求人を探すことができます。細かい要望をヒアリングして希望に近い求人情報をご紹介するので、ぜひ株式会社レソリューションの求人サイトをご活用ください。