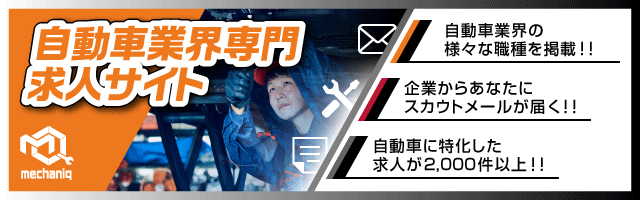自動車は私たちにとって常に必要な移動手段であり、その整備に携わる人の存在も欠かせません。しかし、昨今の情勢から注目される職種群「エッセンシャルワーカー」の1つともいえる自動車整備士が、現在足りていないといわれています。
この記事では、問題となっている自動車整備士不足の背景や、整備士の将来性などをご紹介します。
自動車整備士が不足している原因とは?
なぜ、人々の暮らしに欠かせない職種である自動車整備士の数が足りないという状況が生まれてしまっているのでしょうか。
少子高齢化
わが国では急激に少子高齢化が進んでおり、総人口のなかでも特に労働人口が減少していく傾向が顕著です。このため、業界を問わず慢性的な人手不足が続いており、この状況は好転する見込みがないといわれています。
働く人の絶対数そのものが減っている影響を受け、自動車整備士も足りない状況が続いているのです。
若者の自動車離れ
「若者の自動車離れ」という言葉をよく耳にします。なかなか所得が増える見通しがないなか、さまざまな費用がかかる自動車を所有する意欲がわかないケースです。昨今の若者世代の特色といわれる「コスパ至上主義」も相まった、経済的要因からの車離れといえるでしょう。
それに加え、若者に限らず自動車を持たない人も増えています。特に、電車や地下鉄など公共交通機関が主要な移動手段となる地域では、幅広い世代で自家用車のない世帯が多くなっています。
また、現代は多様化の時代といわれますが、価値観の変化にともなって自動車を持つことへの考え方も変わりました。昭和から平成初期までのように、自動車の保有が社会的ステータスであるという見方が薄くなり、車に憧れる人が少なくなりました。そういった背景が、自動車整備士を志望する人の減少につながっているといえるでしょう。
自動車整備士業界の現状

自動車整備士が減っているとご説明しましたが、実際の減少数や整備士平均年齢、整備工場数の推移はどのような状況となっているのでしょうか。
自動車整備士はどのくらい減少しているのか
日本自動車整備振興会連合会の「自動車分解整備業実態調査」によると、2014年度に342,486人いた自動車整備士は、2019年度には336,897人まで減り、実に5,600人弱もの減少となっています。年間にして1,000人近くの減少となり、数字で見ると深刻な状況がより明確に分かるかと思います。ただし、最新である2020年度のデータでの整備士数は339,593人で、2,696人増加しています。
整備士の平均年齢
自動車整備に携わる人(整備要員)の平均年齢は、2020年度の「自動車分解整備業実態調査」では45.7歳となっています。体を動かす機会が多く活動的な職種としては、平均年齢が高めであるという特徴が分かります。
整備工場数の推移
整備工場の総数は、2015年度で92,160事業場、2020年度は91,533事業場となっています。ほぼ横ばいの状況で、整備士の人数減少を鑑みると人手不足が次第に加速していることが分かります。
自動車整備士の将来性について

整備士不足が叫ばれるなか、整備士をめざしているみなさんは志望職種の将来について考える機会も多いと思います。ここでは、自動車整備という職業の将来性についてもみていきましょう。
整備士不足を反映し需要増が続く
整備士の数が不足する状況は、昨今の情勢から見ても改善する見通しがありません。このため整備士の需要は高い状態がしばらくは続くと考えられます。就職・転職においても「売り手市場(求職者が就職先を選びやすい状態)」が続くでしょう。
国も整備士業界を盛り上げるため取り組んでいる
整備士業界の深刻化する人手不足に対し、国も供給を増やすための取り組みを行っています。
2018年に制度が拡充された厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」は、雇用保険に加入していた求職者に対し、厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練の受講中もしくは修了後に、受講にかかった経費の50%(年間40万円上限)を、原則2年・最大3年までハローワークから支給するものです。
自動車整備課程の受講も専門実践教育訓練にあたるため、整備士をめざす離職者の方も一定条件を満たすと給付を受けられます。
安定した働き方ができる
社会から自動車がすぐになくなったり急減したりすることはなく、整備にあたる仕事もなくなることはありません。自動車整備事業所は、今後も引き続き必要とされることが予測されます。整備士資格を持っていれば安定した働き口を見つけやすく、長く働くこともできるでしょう。
先端技術を習得できる
近年はハイブリッド自動車や電気自動車も普及しつつあり、自動車業界で働いていなければ身につけられない新しい技術をどんどん学べるチャンスが広がっています。
自動車整備士をめざすなら今がチャンス
自動車整備士という職種は、就職や転職にあたっては当面の間は「売り手市場」が続くことが予測できます。また、担い手が絶対数として減っていく見通しを踏まえ、未経験や無資格での就職を視野に入れることも可能です。もちろん整備業で実務経験を積めば整備士資格取得の道が開けますから、どなたでもキャリアアップが見込めるところも魅力。
「経験がない」「資格を持っていない」とあきらめず、整備業界へのチャレンジを考えてみてはいかがでしょうか。

まとめ
自動車整備業は人材の需要が安定して高く、将来性も見込める業種です。しかし、いざ1人で就職活動に臨むには分からないことも多く、ハードルを感じる方もいるでしょう。そんなとき助けになるのが、就職エージェントの存在です。お悩みをお持ちなら整備士・メカニック業界人材会社No.1のレソリューションまでお問い合わせください。